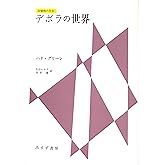良かったです
この注文でお急ぎ便、お届け日時指定便を無料体験
Amazonプライム無料体験について
Amazonプライム無料体験について
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
| 非会員 | プライム会員 | |
|---|---|---|
| 通常配送 | ¥460 - ¥500* | 無料 |
| お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
| お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥3,500以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

分裂病の少女の手記―心理療法による分裂病の回復過程 単行本 – 1971/7/6
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
{"desktop_buybox_group_1":[{"displayPrice":"¥2,640","priceAmount":2640.00,"currencySymbol":"¥","integerValue":"2,640","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"s8Pts1pbsmLCGmJawzhl8VLYuzdD5X0tvP2kIIPldhvvxIagKXxNfSwxaVukIldlCvASG%2Bb%2B8m6%2FxZShYUuBgaeHKk%2B60ZI%2F5%2F%2BZDndp9PXLf77%2Bzx6i96H8jRMpgRZs","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"NEW","aapiBuyingOptionIndex":0}, {"displayPrice":"¥1","priceAmount":1.00,"currencySymbol":"¥","integerValue":"1","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"s8Pts1pbsmLCGmJawzhl8VLYuzdD5X0tnI4%2FMHZSYLwlolnrIgGzljSrjNBOOFlumOd7GkvSJmOvWf3KXrKorwha0DKmlcHc4dE5xW50w%2FxylkmvaF%2Bc7OpDAZwLLUyLwwy4TF%2FNAp86L5Xx5%2BzsIz%2BLGmoGVbl5gPYwov4K1e61X9YLmhFBWw%3D%3D","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"USED","aapiBuyingOptionIndex":1}]}
購入オプションとあわせ買い
本書はルネと呼ばれる少女が、精神分裂病にかかり、著者セシュエー女史の献身的な精神療法によって全快にいたる経過を、ルネ自身が回復後、回想的に記録したもので、本書の後半では、治療者セシュエーが、ルネの罹病及び回復過程を心理学的に分析・説明している。
分裂病が精神療法的措置によって全快にいたった事実は、従来の医学者にとって驚嘆すべきことであった。分裂病の精神病理学において革命的な事件である。本書の刊行が世界的に大きな反響を呼び、相ついで外国語訳が刊行されたのも、もとより理由のあることである。
有名なフランスの哲学者エミール・ブレイエもその著「現代哲学入門」のうちで、本書について次のように評している。
「最近セシュエーが公けにした『分裂病の少女の手記』という驚くべき記録をお読みになってごらんなさい。精神分裂病患者が送っている、さまざまな闘争と口に出さない悩みとはかない喜びとの生活がお分りになります。」
分裂病が精神療法的措置によって全快にいたった事実は、従来の医学者にとって驚嘆すべきことであった。分裂病の精神病理学において革命的な事件である。本書の刊行が世界的に大きな反響を呼び、相ついで外国語訳が刊行されたのも、もとより理由のあることである。
有名なフランスの哲学者エミール・ブレイエもその著「現代哲学入門」のうちで、本書について次のように評している。
「最近セシュエーが公けにした『分裂病の少女の手記』という驚くべき記録をお読みになってごらんなさい。精神分裂病患者が送っている、さまざまな闘争と口に出さない悩みとはかない喜びとの生活がお分りになります。」
- 本の長さ168ページ
- 言語日本語
- 出版社みすず書房
- 発売日1971/7/6
- ISBN-104622023415
- ISBN-13978-4622023418
よく一緒に購入されている商品

対象商品: 分裂病の少女の手記―心理療法による分裂病の回復過程
¥2,640¥2,640
最短で5月10日 土曜日のお届け予定です
残り8点(入荷予定あり)
総額: $00$00
当社の価格を見るには、これら商品をカートに追加してください。
ポイントの合計:
pt
もう一度お試しください
追加されました
一緒に購入する商品を選択してください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
登録情報
- 出版社 : みすず書房 (1971/7/6)
- 発売日 : 1971/7/6
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 168ページ
- ISBN-10 : 4622023415
- ISBN-13 : 978-4622023418
- Amazon 売れ筋ランキング: - 59,163位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 228位ストレス・心の病気
- - 3,072位医学・薬学・看護学・歯科学
- - 7,070位科学・テクノロジー (本)
- カスタマーレビュー:
カスタマーレビュー
星5つ中4.4つ
5つのうち4.4つ
29グローバルレーティング
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星5つ50%36%14%0%0%50%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星4つ50%36%14%0%0%36%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星3つ50%36%14%0%0%14%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星2つ50%36%14%0%0%0%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星1つ50%36%14%0%0%0%
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2021年4月22日に日本でレビュー済みAmazonで購入ありがとうございました
- 2014年1月7日に日本でレビュー済みAmazonで購入統合失調症患者の手記は数ある。
しかしこの手記は頭一つ抜けている。
われわれ患者には世界がどのように迫ってくるのかが、わかりやすい言葉で明快に書かれている。
「物体がむきだしで気味悪い」
「ピカピカと眩しくて世界が迫ってくる。光が私を奪ってしまう」
「自分が膜に包まれたようで、世界が奥行を失ってしまった」
「友人がなわとびを回す、その様子が、意味もなく奇妙でおかしい」
つまり、ある瞬間に突然、世界がグロテスクでよそよそしいモノに変化してしまった、と訴えている。
この感覚は患者本人でないと、いくら文字にしても、絶対に伝わらない。
この本の素晴らしい点は、妄想や幻覚が現れる直前の、病気が発病するかしないかのギリギリの風景が
よく書かれているところにもあると思う。
『シュレーバー回想録』はすでに妄想にかかってからの産物だし、『デボラの世界』は小説としてすこし作られすぎている感が否めない。
『引き裂かれた自己』や『自明性の喪失』は、たしかに患者の内側からの視点を描こうとはしているが、
しかし結局のところ、健康な学者が頭で考えて、自分の関心にひきよせながら再構築した風景であるにすぎない。
学者の描く統合失調患者の世界は、すこし哲学的に洗練されすぎているように感じる。
インテリの人々がうっすらと抱いているらしい 「狂気への憧れ」 はどこか的外れなように思う。
そんな知的な問題に取り組んでいるような余裕は、患者にはないと知ってほしい。
もっと差し迫った肉体的な直感でもって、世界がグロテスクで奇妙なのだ。
本書は妄想や幻覚に移行する直前の、発病する直前の、世界が奇妙にザワつきだす瞬間がよく描写されていて素晴らしかった。
そしてもう一つ重大な点がある。と思う。
少女ルネの病気が寛解する大きな要因は女医の 「愛」 にある、という点だ。
ルネは女医を 「ママ」 と呼び、無条件の愛と庇護を要求する。
そして女医もその要求に応え、ほとんど無尽蔵の愛情を注ぎ続ける。
自分が他人から必要とされ、守られ、そして安全だと確信したルネは、寛解への道を歩む。
これと全く逆のパターンが『自明性の喪失』の事例であるアンネだ。
アンネはルネと同様に愛情を必要としていたが、しかし最後まで誰からも愛を与えられない。
「アンネには精神的に幼稚なところがあり、まるで幼児のように完全なる愛情を欲するが、それは不可能な要求だった」と観察記録が残るのみ。
アンネは最終的に自殺する。
これまでの統合失調症の「実存的分析」というものは、「実存的」と名乗っている割には、患者を人間として捕まえ損なっている感がある。
それは感情の交流にバグのある「間がらの病気」だとか、世界と接続を失ってしまう病気だとか、色々な言い方がなされるが、
どこか哲学的、とくにドイツ観念論の問題意識にひきずられすぎているように感じる。
真に統合失調が「実存的」な病だというのなら、その問題の所在も実存的であるはずであって、
それはつまり、「愛情」だとか「人生における使命感」だとかいった、文学が扱いつづけてきた俗っぽい問題であるように思う。
社会復帰や寛解には、他者からの愛情や、人生における使命感が必要なのかもしれない。
多くの者が 思春期と青年期の境界線で発病するという事実も、これらの問題と無関係でないように思える。
- 2019年4月1日に日本でレビュー済みある本ではげしく勧められていて手に取りました。買った後にみすず書房だときづいてこれはきっと面白い系の本ではないんだなと自分に言い聞かせてから読み進める。自分はまったくの素人なのでお医者さん等のレビューではないのを先に書いておきます。
ルネという少女が精神病から復帰したあとに書いたという内容。10歳前後くらいから話が開始して、自分がどのような幻聴や脅迫をうけて行動していたのか、また周囲はこのように反応していたけど実際はこういうことをかんがえていたのよという内容。正直、本当に回復してから書いたの?という内容である。だいたいの話の流れは終えるが、なんか良く分からないとこも多々。「組織」、「光の国」という暗黒帝国のような幻聴が少女を襲う。最後のほうになると、今まで絶対的な日常を好み、何か周りにあるものが変わるとおかしくなりそうだったのに、部屋のレイアウトを変えても驚かない自分がいるなど、少しずつ自分を客観視した見方もできるようになる。それもこれも、精神科医で「ママ」と呼んでいた女性の治療を受けてからなのであるが、ひとまず本篇はそれで終わる(100ページ)。
残りの50ページは解説である。精神科医が彼女の治療を始めてからの変化、失敗を説明している。これが著書、そして少女からは「ママ」といわれていたセシュエーである(びっくり!)。お医者さん等にはわかるのであろう、難しい話が進むが、あの時の少女の行動はこういうことだったのか、あの変化は快方に向かう、または退化しているということだったのかとわかる。でも、基本は眠い話(50ページ)。
そして、付録。ずっと少女が回想で触れて来なかった、少女の家族の話。なんだ、典型的な愛情欠乏境遇じゃないかと納得せざる得ない内容。少女がふれなかったのも無理はない。
しかも、最後のあとがきではルネという名前が仮名だと明かされた。最後にはみすず書房編集からで今は統合失病症だよとのコメント。Wikipediaをみて、病気の定義も難しいということがわかる。なんか推理小説張りに展開がある。。
- 2018年12月12日に日本でレビュー済みAmazonで購入セシュエー女史の献身性と分裂病少女ルネの二部構成に渡る手記とその分析の記載である。本書は駆け出しの精神医療者にはあまり推奨しない。時代背景が、まだ境界例という概念すらままならない時代の書籍である。ルネはおそらく今でいうとところの境界性PDかと思われるのでそういう視点でちょっと斜めから見た方が読み応えがある。ルネを当時でいうところの分裂病の退行例、今でいう二分認知的でロマンチストな幼児型境界例(かな?)と捉えながら読むと面白い本である。私見だが、身近にいるPDの女性患者とルネが被る瞬間があった。
- 2015年4月13日に日本でレビュー済みAmazonで購入心理学や精神病についてはまったくの門外者ですが、講談社現代新書から出版されていた中村信男さん著の『ナルシズム』を学生時代に読んでいて、この中で語られるシュレーバーの回想録に興味を持ち、探しているときでした。
統合失調症の症状はおおむね知ってはいましたが、先天的なものではなく幼児期の育成環境が大きく病因に関係していることは知りませんでした。岩波新書の『精神分析入門』(著・宮城音弥)なども読みながら進めると理解が深まりました。
また、「小児の自我の建設と、精神病的自我の再建設」とが「同様に利用される」治療の課程なども驚きます。
セシュエー女史による治療課程が記されるP.125からは圧巻です。以下は本書の目次です。
【ルネ本人による手記………第一部 物語】
1. 非現実感の最初の出現
2. 非現実感との闘い
3. リケット
4. 私は精神分析を受けに行き、ママに会った
5. 私は「組織」の命令下に入った
6. 「組織」は私に命令を下し、事物が「存在」し始めた
7. 私は入院したが「組織」は依然として存在し私は危うくママを失うところだった
8. 私は非現実感の中に沈み込んだ
9. 有益な旅行の後に急激な危機が私を混乱させた
10. 私の最初の代役《小さな猿》
11. リンゴの奇蹟
12. 私は自分の体を知ることを学んだ
13. ママの他の患者達により私の自己破壊的エネルギーは解き放たれた
14. ママは「赤ちゃんのエゼキエル」の世話をした
15. 私はママの身体に入りエゼキエルとして生まれ変った
16. 私は美しい現実界に復帰した
【セシュエーによる手記………第二部 解釈】
1. 自我の解体の諸段階
a. 現実の病的知覚の発展
b. 精神病的自我の防衛機制
c. 現実感の口唇期源泉
d. 新しい心的外傷及び自我の胎児期への退行
2. 自我の再建の諸段階
a. 胎児期の象徴的再構成。自我の再建の出発点
b. 病者の新しい“自画像(イマゴ)”の創造
c. 自我形成の手段としての模倣過程
d. 身体的自我の形成
e. 現実の構造の感情的基礎
3. 結論
【附録………ルネの生活歴及び病歴】
【参照文献】
【訳者あとがき】
【改定版へのあとがき(訳者)】
あくまで個人的な意見では、それぞれの手記でルネの生活背景はあまり語られないので、本書附録の『ルネの生活歴及び病歴』を最初に読んでおくほうが内容を理解しやすいように思います。
また、統合失調症の理解では、その症状を疑似体験できるバーチャル・ハルシネーションに大阪市西区社協による講座があるようで、2013年11月6日付の朝日新聞に体験レポが記載され、ネット上で今も同文が読めます。ただしネット会員のみなので、未契約の方は、「SankeiBiz」の「統合失調症への理解深める 幻聴幻視を疑似体験(2014年3月23日)」を検索するとほぼ同じ内容のレポが無料で読めます。
セシュエー女史などについてのプロフィールは71年の改訂版当時のものしか記載されていません。以下は個人的に調べた資料です。
マングリット・アンドレー・セシュエー(Marguerite Andrée Sechehaye 1887年9月27日-1964年6月1日)ジュネーブで死去。夫のアルベール・セシュエー(Albert Sechehaye 1870-1946)はスイスの言語学者で、近代言語学者の父といわれるフェルディナン・ド・ソシュールの薫陶を受けたといわれています。
本書『Journal d'une schizophrène』が初めてフランス語版で出版されたのが1950年。つまり彼女が63歳に著したことになり、本文P.89でルネが、ママは「夫を持っている」ことを挙げることから、夫のアルベール生前にルネの治療を行っていたと思われるので、59歳頃より以前にルネの治療に当たっていたことになります。
Renée(ルネ)については、訳者の後書きのように、恐らくは仮名で、表紙に写る印象的な少女はオリジナルのフランス語版にも採用された装幀ですが、今日の人権擁護との差こそあれ1950年当時とはいえルネ本人ではないと考えるのが妥当かと思います。
彼女のその後ですが、改訂版の後書きでは、セシュエー夫人が亡くなったあと一時的に病気が再発したとあり、以降の動向は分かりません。
ちなみに本書は映画化もされているようで、イタリア映画『JOURNAL D’UNE SCHIZOPHRENE』、英題では『DIARY OF A SCHIZOPHRENIC GIRL』、邦題では『ふれあい』のタイトルで1968年に製作され、ルネはアンナという名に置き変わり、ギスレーヌ・ドルセー(Ghislaine D'Orsay)という少女が演じています。監督はネロ・リージ(Nelo Risi 1920-)。DVDなどは発売されていないようです。